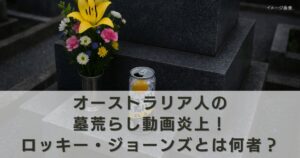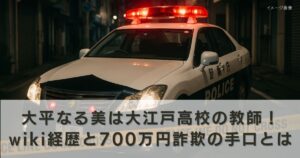女優・三浦透子さんが2025年4月1日に電撃結婚発表され驚かれた方も多いのではないでしょうか。
お相手は音楽家の有元キイチさん。
名前を聞いて「誰?」「どんな人?」と気になって検索された方もいらっしゃるかと思います。
有元さんは表舞台よりも裏方で実力を発揮してきたタイプの音楽家で、知る人ぞ知る存在。
ですが、その音楽性やこれまでの歩みを知ると、なぜ三浦透子さんが惹かれたのかも納得できるはずです。
この記事では、有元キイチさんの人物像、音楽のルーツ、大学時代の活動、そして二人の出会いのエピソードまで、わかりやすくご紹介します。
有元さんの魅力を深掘りしながら、“どんな人か”を丁寧にひも解いていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 有元キイチとは?wiki&経歴を紹介
引用元:https://www.billboard
1-1. 三浦透子の結婚相手として注目
2025年4月、女優・三浦透子さんが結婚を発表し、日本中に衝撃が走りました。
お相手として名前が挙がったのは、音楽家の有元キイチさん。
「誰?」「どんな人?」という声が飛び交う中、ふたりの馴れ初めにも注目が集まりました。
この曲は、有元さんが作詞・作曲・編曲、そしてサウンドプロデュースまで一手に手がけたもので、音楽制作を通して2人の距離が自然と縮まっていったそうです。
作品の中で交わしたやりとりが、やがてプライベートでも深いつながりに発展していった…まさに“音楽がつないだご縁”ともいえるストーリーですね。
1-2. 実は業界注目のギタリスト&音楽プロデューサー
有元キイチさんは、音楽ユニット「ODD Foot Works」のギタリスト・サウンドプロデューサーとして活躍する実力派。
彼の音楽はジャンルレスで、ジャズやヒップホップ、R&Bの要素をミックスしながらも、どこか“空気を感じさせる”独自の世界観が特徴です。
また、佐藤千亜妃さん(元きのこ帝国)や池田エライザさんなど、感度の高いアーティストへの楽曲提供でも評価を受けており、音楽業界内では“静かに燃える才能”として注目されてきました。
表立って話題になるタイプではありませんが、今回の結婚発表を機に、その人物像や実績に注目が集まり、多くの人が「有元キイチって、実はすごい人だったんだ!」と驚かされています。
2. 有元キイチのプロフィール情報まとめ
2-1. 出身地・誕生日・現在の活動拠点は?
有元キイチさんの基本プロフィールは以下のとおりです。
- 誕生日:1995年1月10日(2025年現在で30歳)
- 出身地:東京都多摩市
- 肩書き:音楽家(ギタリスト/作曲家/サウンドプロデューサー)
- 所属:ODD Foot Works
多摩市といえば、東京の中でも自然が多く、穏やかな空気が流れるエリア。
有元さんはそんな土地で育ち、自分らしい感性を伸ばしてきたようです。
音楽活動の拠点は特に限定されていませんが、都内のスタジオやライブハウスを中心に、全国各地での公演・制作も行っている模様。
表に出るタイプではないものの、じっくりと活動を続けている印象があります。
2-2. 東京都多摩市出身の感性が音楽に与えた影響とは
有元さんが育った多摩市は、都会的な利便性と自然の調和が魅力のエリア。
彼自身も「なんでもあるけど、これといって目立つものがない」と語っていますが、逆にその“どこでもない感覚”が、彼の音楽にユニークな世界観を与えているように感じられます。
彼のEP『Tama,Tokyo』には、地元・多摩の情景や記憶が色濃く反映されていて、日常の中にある美しさや孤独が丁寧に切り取られています。
楽曲の中からは、通い慣れた通学路や、静かな駅前、そして淡い青春の思い出が浮かび上がってくるよう。

多摩って地味だけど落ち着くよね~。



私も昔住んでたけど、なんか“ありふれた静けさ”があって、それが音楽になるってすごいと思うわ。
3. 有元キイチの大学時代に迫る
3-1. ジャズ研所属で養った即興性と音楽仲間との出会い
有元さんの大学時代は、まさに音楽人生の土台を築いた大事な時期。
具体的な大学名は明らかになっていませんが、
在学中はジャズ研究会(ジャズ研)に所属していたことが知られています。
ジャズ研では即興性やアンサンブル感を養い、打ち込みだけでは表現しきれない“人と人の呼吸”を大切にする音楽性が形成されていきました。
彼は当時、部室で実際にレコーディングを行い、後にEPにも参加する仲間との関係を深めていったと言われています。
この経験が、ジャンルをまたぐ彼の柔軟な作風に直結しているのは間違いないでしょう。
3-2. Pecoriとの出会いは多摩市のスタジオだった?
有元さんが現在も所属するODD Foot Worksのメンバー・Pecoriさんとの出会いも、大学時代の多摩市のスタジオでのセッションがきっかけです。
当時、有元さんはギタリストとして活動していたものの、まだ曲作りには本格的に取り組んでいませんでした。
そこへ現れたのがPecoriさん。
お互いに「面白そう」と感じたことで意気投合し、音楽制作に没頭するようになったといいます。
部室で打ち込み音源を作り、サックスやキーボードを生録音するなど、手作り感と熱量のある制作環境から、後に評価されるアルバムが生まれていきました。
3-3. 出身大学はどこ?「野猿街道」や「聖蹟桜ヶ丘」から考察
有元さんの出身大学については公表されていませんが、手がかりはあります。
彼がよく通っていたという「野猿街道」や、「聖蹟桜ヶ丘」周辺での学生時代のエピソードから、多摩エリアの大学である可能性が高いとされています。
具体的には以下のような大学が候補として挙げられます:
- 桜美林大学(多摩アカデミーヒルズ)
- 国士舘大学(多摩キャンパス)
- 多摩大学(多摩キャンパス)
- 東京医療学院大学
どれも多摩エリアにあり、彼の発言や活動エリアと一致しています。
仲間と飲みに行った帰りに通った道や、学生時代の記憶が楽曲に反映されていることを考えると、彼の大学生活が音楽に与えた影響は計り知れません。
4. 有元キイチの音楽との出会いと歩み
4-1. 小中学生でギターに触れた多摩のライブハウス「LOOSE VOX」
有元キイチさんの音楽人生は、小学生~中学生の頃に訪れた多摩市のライブハウス「LOOSE VOX」から始まりました。
ただの遊び場ではなく、大人のミュージシャンたちが集う本格的なセッションの場。
そこに、まだあどけなさの残る少年がギターを持って飛び込んだというのだから驚きです。
自分の中にあるものをその場で音にするという、まさに“ライブ”な体験こそが、彼の原点になっています。
その頃のエピソードとして、「友達にライブを見に来てと誘ったら、“1500円のコーラは飲めない”って断られた」という微笑ましい話も(笑)。
こうした経験が、のちの彼の“地に足のついた音楽観”にもつながっているようです。
4-2. セッション文化に触れながら感じた“音の自由”
LOOSE VOXでの経験は、単に演奏スキルを磨いただけではありませんでした。
有元さんが感動したのは「決まった型にハマらなくてもいい」という自由さ。
セッション文化の中では、目の前の空気を感じながら音を紡いでいくという即興性が求められます。
彼はまだ小学生ながら、その文化の真ん中に飛び込んでいき、自分の音を試す楽しさと怖さの両方を体験したのです。
これは、大学時代のジャズ研活動、さらには現在の実験的なサウンドにも直結している要素だと考えられます。



子どもがセッションに混ざるって、なかなかできることじゃないよね〜。



うちの息子もギター始めたけど、LOOSE VOXみたいな場があったら良かったのに!
4-3. 「ゆらゆら帝国」コピーで育った10代の音楽的土台
多くの若いギタリストが通るように、有元キイチさんにも“コピー時代”がありました。
「コピー」とは他のアーティストの曲を自分で音を聞き、楽譜に起こしたりして弾くことです。
彼の音楽的ルーツとして強く影響を与えたのが、伝説的バンド「ゆらゆら帝国」です。
彼は「発光体」や「ラメのパンタロン」などの楽曲を、ギター練習と並行して何度もコピーしたそうで、単なる技術習得にとどまらず、世界観や空気の作り方までを自分の中に吸収していったとのこと。
ゆらゆら帝国のサウンドは、独特のサイケ感や浮遊感を持ちつつ、どこか無機質ではない“人の温度”を感じるもの。
有元さんの音楽に流れる、“聴く者の想像力を刺激する”質感は、こうしたバンドの影響を色濃く受けているのかもしれません。
5. 有元キイチのキャリアを築いたターニングポイント
引用元:https://www.billboard
5-1. ODD Foot Works結成と初期の創作活動
大学時代、有元さんが参加していたのはジャズ研だけではありません。
多摩市・聖蹟桜ヶ丘にあるスタジオで知り合った二人は意気投合し、後に「ODD Foot Works」を結成。
このグループは、ヒップホップを軸にしながらも、ジャズ、ロック、R&Bなど様々なジャンルを縦横無尽に横断する独創的なサウンドが特徴。
有元さんはその中で、ギタリスト兼サウンドプロデューサーとしてグループの音楽的土台を支えています。
5-2. 大学の部室で生まれた実験的サウンドと作品群
有元さんの創作活動は、大学の部室を拠点にしていたという点も注目ポイント。
打ち込みで作成したベーストラックを、ジャズ研の部室に持ち込み、生楽器の録音を重ねるという独特なスタイルで作品を形にしていきました。
この手作り感のある制作手法は、仲間との距離が近いからこそ可能だったもの。
大学の延長線上に生まれたその音楽は、どこか無防備で、人間臭くて、でも洗練されている。彼のソロ作品『Tama,Tokyo』にもその感覚は息づいています。



大学の部室がスタジオ代わりって、青春って感じするわ〜。



そういうのって、音にちゃんと出るのよね、聴いててわかるもの。
6. 【考察】有元キイチの音楽はなぜ人の心をつかむのか
6-1. 多摩という「日常的な非日常」がもたらすリアリティ
有元キイチさんの音楽は、どこか「普通っぽいのに、妙に印象に残る」不思議な魅力を持っています。
その背景には、多摩という土地柄があるのではないでしょうか。
彼自身も「都会っぽいけど特別ではない」と語る多摩は、都市の喧騒と郊外の静けさが共存する独特な空間。
そんな場所で育ったからこそ、彼の音楽には“リアルだけど夢見心地”な感覚が宿っているのだと思います。
聴く人に「どこかで体験したことがあるような懐かしさ」を感じさせるのは、その生活の匂いや記憶が、彼の音にそっと溶け込んでいるからでしょう。
6-2. ジャンルレスでありながら“人の気配”を感じるサウンド
有元さんの音楽は、ヒップホップなのにジャズの空気があって、かと思えばロックのギターリフが響いたりと、実に自由。
けれど、その全てに共通して感じられるのは「人の気配」です。
たとえば打ち込みのトラックにも、どこか人間味がある。
デジタルで作られた音なのに、なぜか手触りが感じられる。
これは、彼が常に“人と作る音楽”を大事にしてきたからに他なりません。
大学時代の部室でのセッションも、LOOSE VOXでの体験も、彼にとっては“他者と音を交わす”貴重な原体験。
その積み重ねが、現在の「人に寄り添う音楽」につながっているのでしょう。
そんな温度感こそが、多くのリスナーの心に届く理由なのかもしれません。